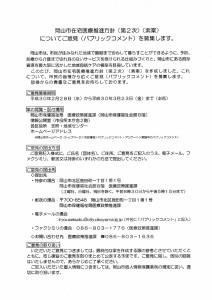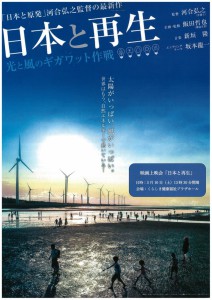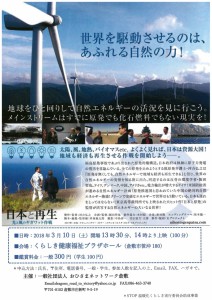市議団事務局(東田) 18年03月7日
(印刷用PDF)竹永光恵(180307)
1 不妊に悩む方への治療支援について
(1)少子化対策の一環として不妊に悩む方への支援強化を
不妊とは「健康な男女が結婚後1年以上にわたり定期的に避妊をせずに性交の機会を持ちながらも妊娠しない場合」と言われています。不妊症の出現率は6組に1組といわれており、特別な事情を持った人々の治療とは言いにくくなっています。また最近は要因の50%が男性にあるとも言われており、男女ともに受診することが望ましいのが現状です。第一子出産時の女性の平均年齢は30.1歳です。早い段階での治療が出生率の増加へとつながると言われています。
ア こういう状況の中で、市としても抜本的に不妊に悩む方への支援を強化する時期だと考えますが、所見をお聞かせください。
(2)不妊治療の各段階での助成の充実を
ア 初期検査にも助成を
国も市も、平成16年度から治療への支援事業を始め、この間8回程度国の制度拡充が行われました。(資料1)
現在は新規申請の助成額上限が15万円から30万円に拡充され、対象年齢も治療初日の妻の年齢が43歳未満へと拡大されています。また、男性の不妊治療に対しても15万円まで助成されるようになりました。
岡山市ではH24年度には898件でしたがH27年度は987件と申請件数が増え、H28年度は若干申請数は減りましたが、助成額では最高となっています。男性不妊の助成は1件から14件に増えています。
不妊に悩む方の一番の課題は経済的負担です。ある民間の調査では、不妊治療によって妊娠された方の平均治療費は140.6万円となっています。そこで伺います。(資料2)
市の助成制度は保険適用外の対外授精の段階の治療になってからです。しかし、保険適用内でも結構費用がかかります。初期検査の子宮がんや子宮頸がんなどがんの検査は最低3回必要で合わせて自己負担が7千円程度必要となります。
そして、排卵期、月経期、黄体期の血液検査、超音波など合わせて一万円程度かかります。
(ア)広島県では、不妊治療を行う上で一番大切なことは、早い段階で原因を明らかにして夫婦そろっての治療を早く始めることだとして、初期検査にも自己負担2分の1(上限5万円)を助成しています。岡山市でも助成すべきと考えますが、いかがでしょうか。
イ タイミング療法から人工授精前検査までの段階
(ア)初期検査のあと次の治療段階はタイミング療法となります。タイミング療法は診察代くらいですが、この治療を4回前後しても受精に至らないときは人工授精をすすめられます。その人工授精ができるかどうかの検査も必要です。卵管がちゃんと通っているかの造影検査や通気検査、フーナ―テストなどがトータルで1万円程度、そのあとの子宮と卵巣が癒着していないかなどの検査もそれとは別に1万円程度かかります。病院にもよりますが、人工授精に至るまで様々な検査があり費用もかかるとのことです。何とか助成できませんか。
(イ)ここまでクリアしてやっと人工授精治療になったとしても、人工授精は1回2~3万円かかります。1回で受精する可能性ばかりではありません。中には10回以上しても受精に至らなかった方もおられました。多くの病院では4回から5回の治療で次の治療段階をすすめるとのことです。最低でも4回分を助成することはできませんか。
ウ 抗体検査など
女性が精子に対して抗体ができていないかを調べる抗精子抗体検査は自費となります。そのほかにも風しんの抗体や感染症などの採血検査も合わせると1万円以上になります。これに助成は出来ませんか。
エ 所得制限と年齢制限について
現在の助成制度は夫婦の所得が730万円未満であり、治療開始時の妻の年齢が43歳未満という条件があります。市によってはその条件を撤廃しているところもありますが、岡山市はどうお考えなのでしょうか。
(3)不妊治療への啓発を
ア 今回何人かの方からお話を伺いました。その中で、不妊治療について自分が直面するまで、全く何も知らなかったという方が多いのが特徴です。そして、夫婦そろっての治療になるまで、夫婦の温度差を埋めるのが大変だったということです。不妊治療そのものの啓発が必要です。栃木県は不妊対策シンポジウムなどを行っています。岡山市も女性がかがやく街づくり推進課が、リプロダクティブ・ヘルス・ライツの視点で啓発事業をしていただきたいが、どうでしょうか。
イ 経済的負担が大きいので、治療中も就労を希望している方が多いのが現状です。しかし不妊治療は女性の性の周期に合わせて行われるため治療スケジュールが難しく、仕事と治療の両立が大きな課題となっています。
また、事業主や上司の不妊治療に対する理解も十分と言えないこと、職場で不妊治療をしていることを言いにくい精神的な負担も多いと伺います。事業所への啓発はどうお考えでしょうか。
(4)相談支援の強化を
市内には岡山大学に不妊治療相談センターがあり当事者によるピアカウンセリングなどを行っています。市内には7か所の指定医療機関があり、個々の病院で説明会やカウンセリングなどを行っていますが、市としては全く取り組んでいないのが現状です。
ア 各保健センターなどで、不妊に悩む方への初期相談ができるよう出張相談日をもうけてはいかがですか。
イ 当事者の方々は、「治療を続けることの大きな負担は精神的なものだ」と言われています。おかやま産前産後相談ステーションに不妊専門相談のできる心理カウンセラーを配置しませんか。
ウ 特に夫婦での意識の違いが縮まらないときなど、女性が一人で悶々と悩むことが多いようです。気軽に相談できるラインなど、SNS等での相談窓口を開設しませんか。
エ 2人目不妊も増えていると伺います。一人目の不妊に悩む方とは別の相談支援や窓口が必要です。子連れで相談できる窓口などもうけていただきたいがどうか。
2 国民健康保険について
(1)制度改正について市民への説明責任は
来年度から国保は大きく制度が変わり、県単位化となります。
市民と岡山市にとって何がどうかわるのか?きちんと市民に説明をすべきだと我が党市議団代表質問で指摘しました。市長は説明責任というよりは情報提供、国保運営協議会で保険料改定の考え方等を説明した、料率については5月に決定、7月に市民に保険料を通知とともに計算根拠も同封のことです。
ア 結局、市民は自分の保険料が確定した時に保険料率が上がったことを知るのです。今後6年間上がり続けることは知らされていません。県が作ったチラシには値上げのねの字もありません。これで説明責任を果たしたといえるのか?
イ このチラシには、県単位化は持続した社会保障制度の確立をめざすためとあります。しかし内容的には社会保障の視点はなく、相互補助の民間の社会保険のような色合いが濃くなっています。今後、医療費の伸びは増えるが被保険者の数は減少するから、国保財政の収支不足が悪化するため、税と保険料の見直しの必要性を値上げの理由としています。
しかし市民の視点で考えると、市は県に納付額を納めるために保険料を上げ続け、払えなかったら差し押さえの強化という悪循環になると思われますが所見をお聞かせください。
(2)国保財政と保険料について
ア 倉敷市の国保財政は平成30年度の歳出総額に対し、歳入予測が8,5億円不足したとのことです。その不足額を補うために繰越4億円と国保財政調整基金の取りくずし1億円を活用し、残りの不足額を一般会計から3,5億円を政策的に繰り入れ、保険料を据え置くという決断をしています。国からは一般会計の政策的繰り入れを削減することについて何の通知も指導もなかったので繰り入れを続けるとのことです。岡山市の、6年で政策的繰り入れをゼロにするという計画は国からの圧力があったのか。国からの通知があったのか、削減計画を作らないことでペナルティがあるのでしょうか。
イ 政策的繰り入れの国の評価基準は『年度を明らかにした具体的な削減計画の策定』であり、岡山市のように全額削減することが評価の対象にはなっていません。削減は制度改正後の状況をみて判断することが求められており、平成31年度以降の削減計画との国の立場です。それならば、平成30年度は岡山市も繰り入れをし、保険料を据え置くことができたのではないですか。なぜ今後上げ続ける選択をしたのか、6年に決めたのはなぜか。
ウ 私たちの代表質問で県への公費負担を求めたことに対し、保健福祉局長は、県費は県が考えることと答弁しました。県の役割は納付金の集金だけなのか、市民はしっかり県民税もおさめています。県の責任を果たすことを求めることは当たり前ではないのか。
エ 国保の構造的課題、高齢者の割合が高く低所得者の多さに起因する財政運営の厳しさは、県単位化で解消されるのでしょうか。
(3)収納率について
国保運営協議会で、収納率向上対策をしっかりと行うことで財政効果が出るのではないかとの意見がありました。
ア 収納率向上への考え方と財政効果をお示しください。
イ 滞納率が20%以上という実態は、高すぎて払えないというのが現状です。資力のないものについては執行停止処分を積極的に展開しませんか。
(4)国保運営協議会について
県単位化に伴い、国保運営協議会のあり方を見直す時です。市は公募の必要性を全く認めていませんが、私たちが傍聴している中では、被保険者代表の委員が全員出席していることはなく、まして全員発言している回は一回もありません。滞納の状況や、差し押さえの状況、払いたくても払えない被保険者の実態などが議論されたことは一度もありません。保険料を滞納し、保険証を取り上げられ病院に行きたくても行けず、倒れて病院に運ばれたという困難事例のケースが年々増えています。
ア 市民のいのちにかかわる実態がまったく話し合われていない運営協議会が、問題がないと言えるのか。改めて公募委員を求めます。所見を。
3 発達障害児の自立に向けた支援について
発達障害者支援法ができてから10年以上たちました。この法律ができた目的は、発達障害のある人が生まれてから年をとるまで、それぞれのライフステージにあった適切な支援を受ける体制を整備することでした。先日も創政会の代表質問で、個別支援の大切さをとりあげておられ、全く同感だと感じました。
個々の障害や発達段階にあった個別支援の中でも、今日取り上げるのは、知的障害を伴わない発達障害の子どもたちへの支援です。
(1)入学前の親の会の皆さんとお話をする機会がありました。最初から通常学級を希望しているのですが、通常学級の情報がなかなか得られなかったとの意見がありました。発達障害児の通常学級での支援について、市としてどう考え、保護者の不安をなくす努力をしていますか。
(2)その時に、発達相談支援ファイル「りんくる」はどういかされますか。
(3)通常学級に通う発達障害児も学校と連携し、支援計画や指導計画の作成ができていますか。
知的障害を伴わない発達障害児は、将来手帳を持たない、また取れない場合もあります。その結果、義務教育終了後はなんの支援もない世界で生きていかなければなりません。小学校入学時、中学入学時、高校入学時、高校生活、大学進学、就職など人生のステージでつまずき、精神障害を併発したり、長いあいだ引きこもったりなどのケースもあるとうかがいます。自立ができるために義務教育の間に社会のルールや、自分の障害の特性、困った感の回避のスキルなどを身につける必要があります。早くからの支援ができていれば、納税者として自立できると思います。それが保護者の大きな願いです。
(4)保護者が通常学級を選んだとしても、教育現場では障害名としてとらえるのでなくその人の特性を知り、困り感を取り除くことが大切です。学級担任だけでは対応が困難だと思います。通常学級の発達障害児に対して、特別支援コーデイネーターや養護教諭、スクールカウンセラーなどチームで支援するしくみをつくりませんか。